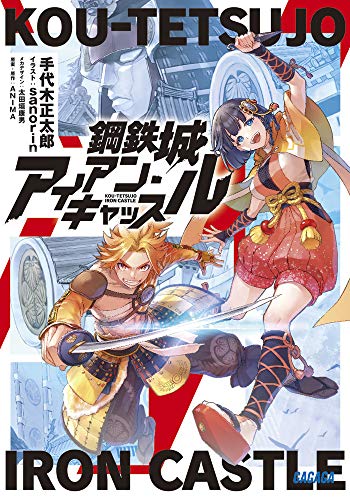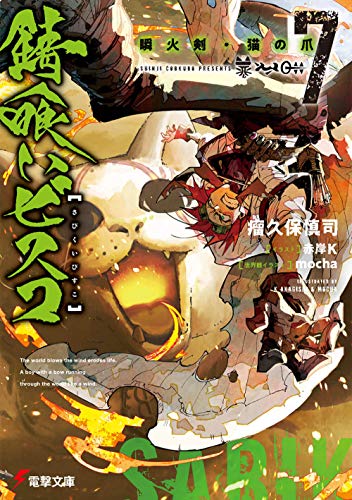PAY DAY 1 日陰者たちの革命【電子特典付き】 (MF文庫J)
- 作者:達間 涼
- 発売日: 2021/03/25
- メディア: Kindle版
生きるために他者の命を奪う。生き残るためには仕方のないことだ。それがようやく、春期にも理解出来た。共に地獄に堕ちた友人と久しぶりに会話をし、どうにか現状を打破出来ないかと糸口を探した。それは結局徒労に終わった。しかし、収穫はあった。
そんな都合のいい希望はどこにも転がっていないのだと、諦めることが出来たのだから。
この町にはヒトを喰らう「日傘の魔女」の都市伝説があった。それから14年。魔女によって仮面の怪物《フォールド》の力を与えられた高校生の鳥羽春樹は、魔女に自分と少女の命を支払うため、「カツアゲ仮面」としてヒトの命を奪い続けていた。魔女に脅され、警察に追われる春樹の前には更に、完全無敗のヒーロー、ブレイズマンが立ちはだかろうとしていた。
まあ実際のところ、祈ったところで神様が助けてくれることもないだろう。
人を助けるのはいつだって、ただの人なのだ。
だからこそ、咄嗟に飛び出して行った彼女の背中はとても尊いものに見えた。
第16回MF文庫Jライトノベル新人賞審査員特別賞受賞作。魔女は言った、命を稼ぎなさいと。殺されないために自分の命を賭けてヒトの命を奪う仮面のヴィランたちの話から始まり、大切な誰かを守るために生きるヒーローの誕生と終わりの物語に収束する。カツアゲ仮面こと春樹と、ブレイズマンのふたりの主人公ともに主要な人物の家族関係が良好なものとして描かれるのがあまり見ない新鮮な感じだった。物語の緩急にちょっと難があったり、新人賞らしい粗さもあちこちに見られるのだけど、正義と悪を問う王道の変身ヒーロー小説だったと思います。
それから春樹は、彼の勇姿を目に焼き付けようと、その場に座り込んだ。
戦いに赴くヒーローの姿には目を奪われた。そしてふと、妙な物悲しさも覚えるのだ。
空に瞬くブレイズマンの戦いを眺め、ああ、花火に似てんだ。そう春樹は思った。